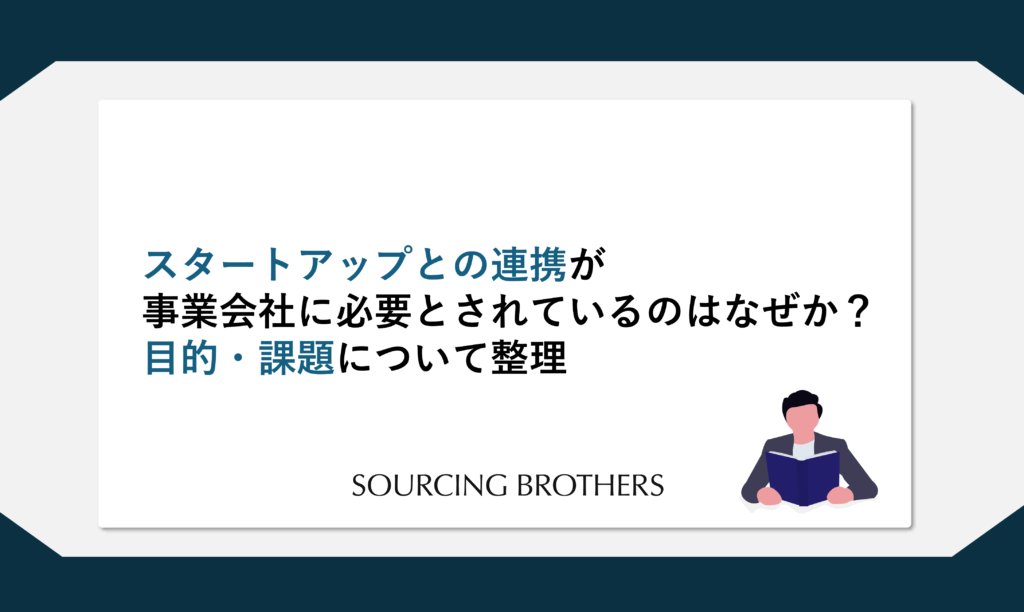スタートアップ連携についての資料をダウンロードする⬇️
目次
スタートアップとの連携が必要とされている理由
「オープンイノベーション」「スタートアップ連携」——。ここ数年、これらの言葉を耳にしない日はありません。一時的なブームではなく、もはや多くの事業会社にとって避けては通れないテーマになっています。
では、なぜこれほどまでにスタートアップとの連携が求められているのでしょうか。
自前主義の限界が見えてきた
日本企業の研究開発費を見ると、その約9割を大企業が占めています。一見すると、資金も人材も潤沢に見えるかもしれません。しかし実態は違います。
これらの研究開発費の多くは、既存事業の改善や効率化に使われています。つまり、今ある製品やサービスをより良くすることには長けていても、まったく新しい市場を切り拓くような革新的な新規事業の創出となると、どうしても手薄になってしまうのです。
技術革新のスピードは加速し、市場の変化も激しさを増しています。こうした環境下では、自社の研究開発だけに頼っていては、新しい事業の芽を育てることが難しくなってきました。
スタートアップが持つ、大企業にない武器
一方で、スタートアップはどうでしょうか。
彼らの強みは、何といっても意思決定の速さとリスクテイクの姿勢です。大企業のように複雑な承認プロセスを経る必要がなく、新しい技術やビジネスモデルに集中的に投資できます。失敗を恐れず、小さく試して素早く軌道修正する——。この機動力こそが、イノベーションを生み出す原動力になっています。
大企業が持つ資金力・顧客基盤・信用力と、スタートアップが持つスピード・柔軟性・革新性。この2つが組み合わさることで、単独では生み出せなかったイノベーションが可能になります。経済産業省も、こうした連携がイノベーション循環をつくる重要な手段だと位置づけています。
国を挙げた後押しも始まっている
政府もこの動きを強く後押ししています。
経済産業省が策定した「スタートアップ育成5か年計画」では、①人材・ネットワーク、②資金供給、③オープンイノベーションを3本柱に掲げました。スタートアップとの連携は、単なる企業の選択肢ではなく、国の成長戦略における重要な要素として明確に位置づけられているのです。
実際、日本企業によるスタートアップ投資も急拡大しています。大手企業を中心に新規事業創出や既存事業の変革を目的とする企業が増えています。つまり、単なる投資ではなく、事業そのものを変えるための手段として活用されているのです。
グローバルでも存在感を増す東京
国際的に見ても、東京のスタートアップエコシステムは着実に成長しています。世界のスタートアップエコシステムランキングで、東京は初めてトップ10入りを果たしました。
これは単なる順位の話ではありません。有望なスタートアップとの連携力が、事業会社の競争力を左右する時代になったことを意味しています。
社会課題こそが、成長のチャンス
日本企業が直面している課題は山積しています。人口減少による人手不足、GX(グリーントランスフォーメーション)やDX(デジタルトランスフォーメーション)への対応——。
これらの課題は、既存事業の延長線上では解決が困難です。むしろ、自社にはない技術や人材、そしてスピードを持つスタートアップと手を組むことで、課題解決と同時に新たな成長機会を掴もうとする動きが広がっています。
次章では、実際に事業会社がスタートアップとの連携を進める際、どのように「目的」を整理すべきかについて解説していきます。

スタートアップとの連携の目的
「とりあえずスタートアップと組んでみよう」——。
こんな曖昧なスタートで始めた連携プロジェクトの多くは、実証実験止まりで終わります。半年、1年と時間をかけてPoCを回しても、結局何も残らない。そんな”やってみた”オープンイノベーションに陥らないために、まず明確にすべきなのが「目的」です。
では、事業会社がスタートアップと連携する目的とは、具体的に何なのでしょうか。代表的な3つの目的を見ていきましょう。
新規事業・新市場の創出
最も分かりやすい目的が、これまで自社になかった新しい事業や市場をつくることです。
かつて企業のイノベーションは、自社の研究開発部門が中心でした。しかし今、世界中で「クローズドイノベーション」から「オープンイノベーション」へのシフトが進んでいます。つまり、外部のアイデアや技術を積極的に取り込む方向へと舵を切っているのです。
その効果は数字にも表れています。ある調査によれば、大手企業の約8割がオープンイノベーションに取り組んでおり、新製品・新サービスの開発期間が平均で約4割短縮、コストも3割以上削減できたと報告されています。
スピードとコストの両面で優位性があることは明らかです。自社だけでは何年もかかる新規事業の立ち上げを、スタートアップの発想力と機動力を借りることで一気に加速させる——。これが第一の目的です。
既存事業の高度化・DX/GXの加速
新規事業の創出だけが目的ではありません。既にある事業を強化し、競争力を高めることも重要な狙いです。
デジタル技術の進化、カーボンニュートラルへの対応。これらの変化は驚くほど速く、自前ですべての技術や人材を揃えようとすれば、あっという間に時代に取り残されてしまいます。
経済産業省も「オープンイノベーションの推進」をスタートアップ政策の柱の一つに掲げており、スタートアップの製品やサービスを事業会社が調達・購買しやすくするための共創ガイドラインを整備するなど、連携を後押ししています。
つまり、DXやGXに必要な最新技術を「つくる」のではなく「買う」「組む」ことで素早く取り込み、自社の事業変革を加速させる。これが第二の目的です。
既存事業が成熟している企業ほど、この視点は欠かせません。
組織・人材の変革(ケイパビリティ構築)
三つ目の目的は、一見すると意外かもしれません。それは、組織そのものを変えることです。
スタートアップとの共創プロジェクトを通じて、自社の社員にアジャイル開発やリーンスタートアップ型の検証プロセスを体験させる。これ自体を目的にする企業が増えているのです。
具体的には、こんな狙いがあります。
- 社員に”0→1″の事業づくりを経験させる
- 社外との共創に慣れた人材を育てる
- 失敗を許容するカルチャーをつくる
大企業では、新規事業の経験を積める機会は限られています。既存事業の運営や改善が中心となり、ゼロから何かを生み出す経験は希少です。
しかし、スタートアップとの連携プロジェクトなら、そうした経験を意図的につくれます。オープンイノベーションは、新規事業だけでなく、経営人材や事業開発人材を育成するプログラムとしての側面も持っているのです。
実際、こうした取り組みを通じて、社内の空気が変わったという声は少なくありません。「うちの会社でも新しいことができるんだ」という実感が、組織全体の活力を生み出します。
目的が曖昧なまま進めてはいけない
ここまで3つの目的を見てきましたが、重要なのは「自社はどれを優先するのか?」を明確にすることです。
新規事業の創出なのか、既存事業の強化なのか、それとも人材育成なのか。この優先順位を経営陣と現場で共有し、明文化しておかなければなりません。
目的が曖昧なままスタートすると、個々の案件を評価する軸も定まりません。結果として、どのプロジェクトも中途半端に終わり、”やりっぱなし”の取り組みになってしまいます。
「何のためにスタートアップと連携するのか?」
この問いに対する答えを、関係者全員が同じ言葉で語れる状態をつくること。それが、成果を生むスタートアップ連携の第一歩です。
次章では、この目的を踏まえたうえで、実際にスタートアップとの連携を進める際、どのような課題が顕在化しやすいのかを整理していきます。
スタートアップとの連携で見えてくる課題
「スタートアップとの連携を始めてみたものの、なかなか前に進まない」——。
こうした悩みを抱える企業は少なくありません。実際、スタートアップ連携を本気で進めようとすると、多くの企業で共通して浮かび上がる壁があります。それが「経営層」「プロセス・ノウハウ」「マインドセット」の3つです。
調査データを踏まえながら、スタートアップ連携が行き詰まる理由を整理していきましょう。
経営層の課題:ビジョン・KPI・リソース配分
スタートアップとの連携を掲げていても、経営層のコミットメントが不十分だと、現場の取り組みはすぐに行き詰まります。
NEDOのオープンイノベーション調査によれば、社内で取り組みを推進できている企業には共通点があります。それは「経営トップが全社ビジョンと一体でオープンイノベーションの意義・目標を明確に示し、10〜20%の研究開発費を割り当てるなど、必要なリソースを継続的に配分している」ことです。
一方、CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)の調査では、こんな課題が上位に挙がっています。
- 「CVC活動の目的・目標が経営レベルで合意されていない」26%
- 「経営層の関心や優先度が低い」22%
これらは、スタートアップ連携全般に当てはまる課題です。
トップが「なぜやるのか」「どの時間軸で何を期待するのか」を明文化せず、既存事業と同じ物差しだけで評価してしまうとどうなるか。
「短期で売上が出ないから打ち切る」 「PR目的の単発イベントで終わる」
こうした状況に陥ってしまうのです。
経営層の課題は、突き詰めれば3つに集約されます。「戦略と一体のビジョン設計」「専用KPIの設計」「継続的な投資判断」。これらが欠けていると、どんなに現場が頑張っても成果には結びつきません。
プロセス・ノウハウの課題:PoCから事業化までの”型”がない
次に大きいのが、プロセスやノウハウ面の課題です。
日本企業の新規事業のうち、収益化まで到達できた企業は全体の約14%程度に留まるというデータがあります。多くのプロジェクトが資金難や社内抵抗によって「死の谷」を越えられないのです。
特に、PoC(概念実証)ばかりが増え、本格的な事業化に進まない「PoC貧乏」は、スタートアップ連携の現場でよく聞かれる悩みです。
なぜこうなってしまうのでしょうか。背景には、次のようなプロセス・ノウハウの不足があります。
まず、スタートアップの選定からPoC、そして事業化までの一連の「標準プロセス」が社内で設計されていません。PoCのKPIも技術検証が中心で、「事業性」へつなげる評価軸がないケースが多いのです。
さらに、CVC、事業部、経営会議の役割分担と意思決定フローが不明瞭で、スピードが出ません。
実際、CVCの課題調査では、こんな声が聞かれます。
- 「KPIが具体化できず活動評価がしにくい」
- 「事業部から協力を得にくい/干渉される」
- 「意思決定権限が小さく調整に時間がかかる」
いずれも「組織プロセス」に起因する課題です。
全国イノベーション調査でも、企業規模を問わず次のような阻害要因が挙げられています。
- 「能力のある人材の不足」
- 「本業優先などの異なる優先事項」
- 「組織文化・従業員の抵抗」
つまり、多くの企業が直面しているのは、こういう状況です。
オープンイノベーション部署やCVCと事業部を橋渡しする「ミドル層のコーディネーター人材」が足りない。契約、知財などスタートアップ連携特有の実務ノウハウも不足している。
プロセスと人材の両面で「型」がないこと。これが、スタートアップ連携の大きなボトルネックになっているのです。
マインドセットの課題:自前主義と失敗回避文化
3つ目の壁は、最も目に見えにくいものの、最も根深い課題かもしれません。それがマインドセットです。
NEDOの報告書では、オープンイノベーションを推進するために克服すべきポイントとして、自社技術への過度なこだわりや「NIH症候群(Not Invented Here:自社発でないものを拒む傾向)」からの脱却が必要だとしています。
全国イノベーション調査でも、大企業ほど「組織文化・従業員の抵抗」が阻害要因として強く現れると分析されています。
スタートアップ連携の現場では、具体的にこんなマインドが障害として表面化します。
- 「自社でつくれない技術に頼るのは負けだ」という自前主義
- スタートアップを「パートナー」ではなく「下請け」として扱ってしまう姿勢
- 小さく試して学習するより、「最初から完璧な計画」を求める文化
- 失敗が個人評価の大きなマイナスになりやすく、誰もリスクを取りたがらない
こうしたマインドセットは、経営層から現場まで、階層ごとに異なる形で現れます。
トップは「本業を揺るがすリスク」を過度に恐れます。ミドルは「評価されない仕事」に時間を割きたくないと考えます。現場は「失敗できない」プレッシャーから、安全なPoCだけを選ぼうとします。
こうした連鎖が起きてしまうと、どれだけ制度やプロセスを整えても、スタートアップとの真の連携は実現しません。
課題の解決策 ― 「仕組み」と「人」を同時に変える
前章では、スタートアップ連携がつまずきやすい3つのポイント——経営層、プロセス・ノウハウ、マインドセット——を整理しました。
では、これらの課題をどう乗り越えればいいのか。ここからは、実務的に取り得る解決策を、既存の調査や事例を踏まえて具体的に見ていきます。
経営層の課題への解決策:戦略・KPI・リソースをセットで設計する
NEDOの「オープンイノベーション白書」では、成功している企業の共通点として、「全社戦略の中にオープンイノベーション戦略を位置づけ、明確な目標を設定している」ことが挙げられています。
つまり、経営層の課題を解くには、次の3点を「セット」で設計することが不可欠です。
全社戦略への組み込み
中期経営計画の中に、スタートアップ連携で解決したいテーマを明記します。たとえば「新規事業を〇件創出」「GX/DXテーマへの対応」「海外展開の加速」といった具合です。
重要なのは、自社のケイパビリティを超える挑戦目標をあえて設定すること。「だからこそ外部と組む必要がある」というストーリーに落とし込むことで、社内の納得感が生まれます。
専任組織と予算・権限の付与
NEDOの分析によると、成功企業はオープンイノベーション専任組織を設置し、ミッション・権限・予算を明確に付与していることが共通しています。
「本業の片手間」でスタートアップ連携をするのではなく、コーポレート部門と事業部門の橋渡しを担うチームに、意思決定権を含めて任せる。これによって、スピードと継続性が生まれるのです。
プロセス・ノウハウの課題への解決策:PoCから事業化までの”型”づくり
多くの企業で問題になるのが、PoCまでは行くが事業化に進まないことです。
新規事業の「死の谷」を越えた企業の共通点として、PoC → PoB(事業性検証)→ 本格ローンチまでのステージゲートと、各段階のKPIが設計されていることが指摘されています。
具体的な解決策を見ていきましょう。
標準プロセス・チェックリストの整備
まず必要なのは、連携の一連の流れを標準化することです。
「テーマ設定 → スタートアップ探索 → 初期検討 → PoC → PoB → ローンチ」という標準フローを定義し、各ステージごとに「次に進む条件(KPI)」と「やめる条件」を明文化します。これによって、案件ごとの属人的な判断を減らせます。
さらに、契約・知財・情報セキュリティなどもテンプレート化しておきましょう。毎回ゼロから社内調整をしなくて済むようになれば、スピードは格段に上がります。
PoC設計の段階で”事業化の筋書き”まで描く
PoCの失敗要因として「PoC実施前のゴールや事業化の絵が曖昧なまま始めること」があります。
解決策は、事前にビジネスモデル案・ターゲット市場・成功条件をセットで検討することです。
PoC開始前に、「うまくいった場合、どの事業部で、どのプロセスに組み込むのか」を決めておく。評価の観点にも、技術だけでなく「顧客価値」「収益ポテンシャル」「スケール可能性」を含める。
こうした準備が、PoCを事業化につなげる鍵になります。
マインドセットの課題への解決策:失敗から学ぶ文化と「両利き経営」
NEDOの分析では、オープンイノベーション成功要因として、トップの理解・コミットメント、ミドル層の「橋渡し」機能、現場のイノベーター人材の発掘・活用、そしてイノベーションを促す組織文化・風土が挙げられています。
この”ソフト面”の課題を解くためのアプローチを見ていきましょう。
「小さく失敗できる場」を制度として用意する
一定額以下のPoCであれば、部門長レベルで迅速に決裁できる「クイックPoC枠」を設ける。
PoCの結果が事業化につながらなくても、「学び」や「社内ノウハウ化」の観点で評価するよう、評価制度側も調整する。
PoCで得た経験を次のプロジェクトに活かす姿勢を持つことが、事業会社にとって重要です。失敗を責めるのではなく、そこから何を学んだかを評価する。この文化が根付けば、現場の心理的ハードルは大きく下がります。
コーディネーター人材の育成・配置
成功事例では、経営と事業部、スタートアップの間を橋渡しするミドル層が重要な役割を果たしています。
新規事業やM&A経験者、技術とビジネスの両方が分かる人材を中核に据えましょう。社外コミュニティやピッチイベントへの参加を通じて、担当者自身が”顔の見えるネットワーク”を持てるようにすることも効果的です。
人材配置は、制度やプロセスと同じくらい、場合によってはそれ以上に重要です。
外部パートナーの活用:自社だけで”全部やろうとしない”
「外部ネットワーク・コミュニティの形成」「外部仲介業者の活用」も重要なポイントです。
スタートアップ連携には、スタートアップの目利き、契約・出資スキームの設計、社内外ステークホルダーの調整など、専門性の高い要素が多く含まれます。すべてを自社内で賄おうとすると、立ち上げに時間がかかり、担当者にも過度な負荷がかかってしまいます。
そこで有効なのが、外部のイノベーションパートナーの活用です。
- 連携目的・テーマの整理(スタートアップ連携の目的の言語化)
- プロセス・KPI設計(PoC〜事業化の型づくり)
- スタートアップのソーシング・マッチング
- CVC・事業提携・M&Aの選択肢整理
こうした部分を外部の専門家と一緒に設計することで、社内の立ち上がりを大幅に早めることができます。
仕組みと人、両方を変える
ここまで見てきた解決策は、「仕組み」と「人」の両面にまたがっています。
プロセスやKPIといった仕組みだけを整えても、人のマインドセットが変わらなければ機能しません。逆に、マインドセットだけを変えようとしても、具体的な仕組みがなければ現場は動けません。
大切なのは、両方を同時に、段階的に変えていくことです。
まとめ
スタートアップ 連携が必要とされる背景には、技術革新のスピード、人口減少・人手不足、GX・DXといった構造課題があり、もはや一社単独ではイノベーションを生み出し続けることが難しくなっている現実があります。
そのうえで、スタートアップ 連携 目的は
- 新規事業・新市場の創出
- 既存事業の高度化やDX/GXの加速
- 組織・人材の変革(新規事業人材育成)
- CVC等を通じた事業シナジー+財務リターン
- 社会課題解決と企業価値向上と多層的であり、本来は自社として優先順位を明確にしておくべきものです。
一方で、多くの企業が直面するのは、経営層のコミット不足、PoC止まりになるプロセス・ノウハウの欠如、自前主義や失敗回避といったマインドセットの壁です。これらは個別の問題ではなく、相互に絡み合いながら、スタートアップ 連携のスピードと質を下げてしまいます。
解決の方向性としては、①経営戦略の中にスタートアップ連携を正式に位置づけること、②PoC〜事業化までの“型”とKPIを設計すること、③小さく試し、学びを評価する文化とコーディネーター人材を育てること、そして④自社だけで抱え込まず外部パートナーやエコシステムを活用することが挙げられます。
まずは、「なぜ自社はスタートアップと連携するのか?」を社内で言語化し、関係者で共有することが、すべての起点になります。ここから先は、自社のフェーズに応じて、できるところから一つずつ仕組みと人を整えていくことが重要です。